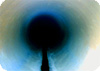 さざなみに食べられて
さざなみに食べられて
きれいな人間だ、そう思った。その浮世離れは徹底されたもので、作り物だとわかっているのに騙される。
「嶺岸長春」よく通る、低すぎも高すぎもない耳に優しい声だ。
元来ぼくは身体のつよい人間ではなかった。だから小学の時分から体育の授業には出たためしがない。中学、高校では定期試験のときに受ける筆記試験と数ヶ月にひとつ課せられるレポートから成績がつけられた。教師は病弱だと言うぼくを気遣って保健室で寝ていろなどと言ったが、そう昼間から眠れるわけもないだろう。そんなことで万一次の授業に支障をきたしでもしたら癪であるし、まずもってベッドの準備や片付けをするのも面倒くさい。教室か図書室で自学をしていますと嘘を吐いては非常階段で本を読んだ。風通しもほどよいし、寒いときは日差しに当たり暑いときは影に座りと調節もできて快適な場所であったからだ。三階の一番奥であったので、授業中にこんな場所に来る人間もいない。ささやかなたのしみ。高校生のことだ、いけない行為を働くことへの妙な背徳感と言うべきか、不思議な高揚感もあった。誰も来ない、誰も通りかからない、ぼくはそう知っていた。油断もなにも、気を払う必要がなかったのだ。それで、しかも彼には気配もなかった。唐突に背中に向かって投げつけられた言葉に驚き振り返るより先に、強く肩を掴んで突き飛ばされた。盛大にバランスを崩してしたたかに腰から後頭部にかけてを床に打ち付ける。いたい。こんなに痛い思いをしたのは久方ぶりだ。いたい。背中を暑さのせいだけでない汗が伝う。薄く目を開けるとぼくと同じ制服を着た人間が笑っていた。きれいな人間だ、そう思った。
「嶺岸長春。はる、春だ」もう一度制服を見てようやくこいつが男であることを認識して、それからぼくは彼に押し倒されているのだという状況を理解する。幼少のころはほとんどの人間から今彼が言ったものと同じように呼ばれていた。しかし中学の時分に美術教師が配ったプリントに江戸時代の浮世絵師宮川長春が載っていたことからずっとぼくのあだ名はシュンだ。はる、そのやわらかい発音がぼくに向けられることは耳にあたたかく懐かしかった。痛みからぼんやりしている頭をなんとか覚醒させようと試みる。
「春、おれのセフレになってよ」
甘い声が耳から入って脳を侵す。溶かされそうだ。せふれ、セフレ? セックスフレンドのことだ。言葉は知っている。前に読んだ小説にあった。「なに、を」こんなきれいな顔でそんな卑猥な言葉を口にするなんて間違っている。その念だけが頭にあった。「おれを犯して」そんなきたない言葉を口にするな。徐々に頭は声を言葉として意味を脳へ伝達する。「だめだ」「どうして」薄い笑みを浮かべて、可愛らしく首を傾ける。頭がいたい。「彼女がいる」「セックスしてくれるだけでいいよ」「できない」「彼女なんて関係ないだろ」「そんなことない」「人格者なんだね」「普通だ」
ぐ、と喉がなった。胸ぐらを掴まれているのだ。わざとか自然か、体重がかけられて喉がしまる。くるしい。
「男とするのが嫌かな。大丈夫、慣れればなにも問題ないよ」ねえ、と甘えた声をだして熱い息がぼくの顔にかかった。女の子のようなにおいがした。できない。狭い喉からしぼりだす。「できない。いや、じゃなくて」はっとしてぼくの上で笑う男を見る。男を性欲の対象として見たことはない。想像するだけで気持ちが悪い。だというのに、なぜだ。ぼくは今彼に少しも嫌悪感を持っていない。それどころか、彼女と初めて関係を持ったときと同じくらいどきどきしている。身体中があつい。はあ、と息が漏れる。ぼくの襟を掴む手から、ワイシャツやズボン越しに触れる身体から彼の熱が伝わってくる。他人に触れるとはこういうことだった。ぼくの頭はすっかりやられて、つよくかたく目を瞑る。するとふと先刻よりももっと近くで息がかかって、あ、と目を開くと綺麗な顔がぼくに近づき薄いながらも柔らかな唇がぼくに触れた。ぞくと心臓が高鳴り肌が粟立って逃げようともがくのだけれど襟をがっちり掴まれている。首を横に動かして避けるなどということは思いつきもしなかった。唇を舐めて吸われて咥内まで侵される。舌の先でていねいに歯列をなぞられて、肩と腰がびくびくと跳ねた。唇の感触と舌の味を記憶してしまうほど長い時間がたち、ようやく唇が離れた。夢のような心地。
「こわがらないで、春はおれを好きになる」そう断言されてしまえば、根拠もなく真実だと思わずにはいられなかった。
目蓋が重く、今にも閉じてしまいそうだった。一度そうなれば最後、数時間は開けない。ぼくはなんとか目を開き続けようとした。長いキスで上気した彼の顔をもっと見ていたかった。
「きみは、」「桃川清水」
目を細めてふわりと笑う。なんて、きれいな人間だ。自分のものとは思えないほど甘く、熱に浮かされた声でぼくはその名を呼んだ。